第10話「赤点×パニック×天の声」
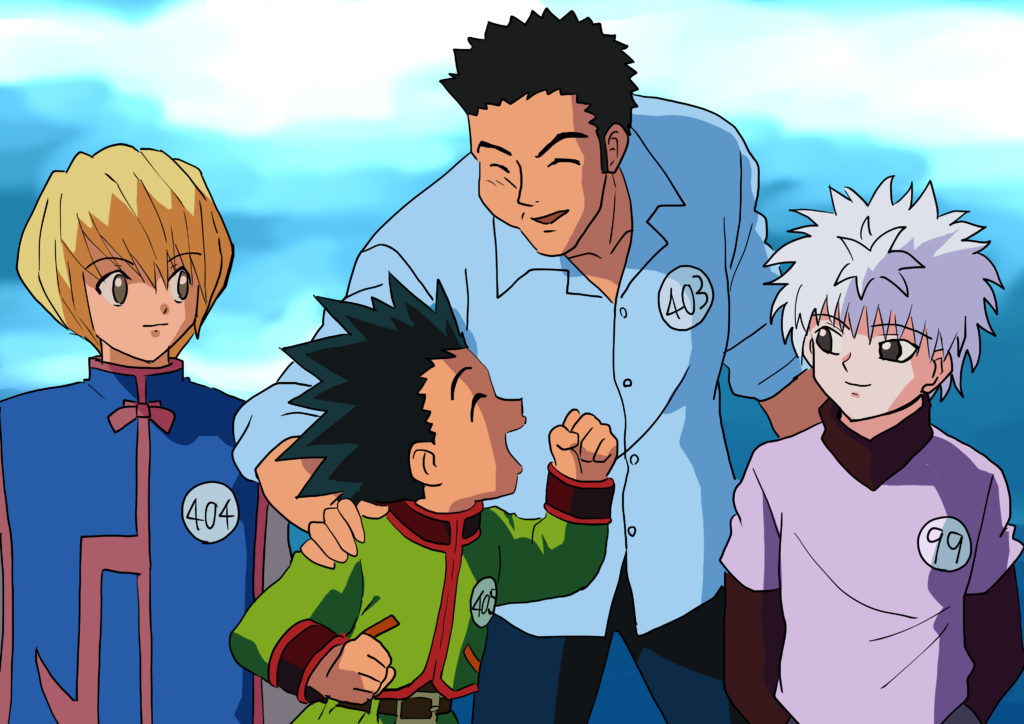
※注意点
このシリーズはハンターハンターのアニメを深読みして、自分なりの感想をまとめたものになります。
そのため、主観的な意見が多く、証拠や根拠はあまりありません。
私が見て感じたことや気づいたこと、大切だと思ったことなどを正直に書いているだけのものですので、
十分理解した上で読まれることをおすすめします。
こういった感情や見方で見る人もいるのだと思っていただけたらば幸いです。
Aパート
・試験はこれで終わりだとメンチが宣言するとキルアは「ばかくせー」と呆れ、ゴンは真剣な声で「そんな。これで試験終わっちゃうなんて」と残念がる。
キルアは、そんなゴンを驚いて見つめる。
毎年ある試験なのだから、そんなに残念がらなくても、と思ったのか、いつも前向きで明るいゴンが今回ばかりはショックを受けているのに驚いたのか、自分はゲームのつもりだったからそのリアクションの差に戸惑ったのか。何らかの気持ちが考えられる。Bパートで「よかったな、ゴン」と声をかけているから、ゴンの必死さを少し心配というべきか、気にしてはいたのだろう。
・「合格者はゼロ」と電話口でも譲らないメンチ。そのメンチの受話器を取り上げ、「ちょっとタンマ。タンマだからね!」と伝えるゴン。
怒るメンチに「ハンター試験に受かって父さんに会わなきゃいけないんだ」とゴン。のちの本試験でもわかるとおり、ゴンは「今回で」受かる事が無意識の中に重く大きく存在していることが、ここのシーンでもわかる。「次、来年受けられればいい」「来年また来よう」などという軽い気持ちは一切ないのだろう。
そしてメンチに「もう一回やり直すって言ってくれればいい」と言う。
メンチはそれでも譲らない。彼女は自分の信念がしっかりしているゆえに、一度決めたら絶対に譲らない性格をしていると言えるだろう。(ただ、間違いに気付けばそれを直す素直さも持っている。詳しくはBパートで述べる)
・「納得いかねぇな」とトードーが台を叩き壊す。
続けて「美食ハンターごとき」とトードーが言うとメンチはそれに反応を示した。
おそらく今までの描写からわかるとおり、その「美食ハンター」に全てを捧げ、シングル持ちにもなっているメンチだ。彼女にとって大きなプライド、誇りがあり、一番大切な部分。そこを、まさにトードーという「受験生ごとき」にほじくられるのだから、良い気分はしないはずだ。
・ブハラがメンチに「こいつを料理しちゃうだろ?」といい、庇う。それに対し、キルアは「へぇ、その料理ってやつ、ちょっと見てみたいな」と述べる。
キルアはこのような緊迫した場面でも余裕を見せる。よほど自分の実力を知り尽くし、それに自信がなければできないことだ。前話もそうだが、実力を見せず隠しつつも、「只者ではない」描写をしっかり挟んでくることで、キルアへの興味を掻き立たせている。これは、二次試験以降に入るキルアの正体が明かされる場面、活躍する場面等に説得力や迫力を持たせるのに十分な役目を果たしていると言える。スタッフの細かい気遣いが感じられ、好感が持てる。
・「1時間ほど待っててちょうだい」とメンチはのべ、どこかへ去っていく。
その後1時間ちょうどで帰ってきて、ツノゴケを見せるメンチ。苔をふりかけにして、振る舞うメンチだが、トードーは食べようとしない。そんな彼の代わりにと、ゴンは抑えきれない様子で「じゃあ、オレが食べるね」と何の躊躇もなく口へ運ぶ。
止めるレオリオだが、キルアは「ゴンなら大丈夫かどうかぐらいわかるさ」と述べる。(原作と新アニメではトンパの無味無臭の下剤が入っているジュースに違和感だけで、おかしいとわかっている)旧ではそのシーンがないから、キルアは一次試験の間に、ゴンは何かしら感覚に優れているのだろうと理解したことになる。犬のような嗅覚があるゴンなら味覚だって常人とは違うのではないかと推察したのかもしれない。また、キルアのペースについてきていたゴンに一目置いていたから、というのもあるだろう。
・レオリオに味の感想を求められるも、よくわからないゴン。
「こんな味、初めてだもん。不思議な味としか言いようがないよ」というが、そこでメンチが説明を入れてくれる。ヌメーレ湿原のさらに奥に生息するオオツノグマのツノゴケだと判明。「坊やにわからないのも無理ないわ」との発言から、いわゆる「大人の味」というものなのかもしれない。貴重なもの、珍味にありがちなことだ。
・「湿原のさらに奥まで行って取ってきただと!?」
「かすり傷一つ負わず、しかも往復1時間足らずで…」
「結構やるじゃん」
とレオリオ、クラピカ、キルアはコケのことよりも、それを取ってきたメンチの常人離れした体力、行動力に注目、賞賛し、関心を示す。
珍味のことも教えることができ、なおかつ自分の基礎体力も言外に示すことのできる、メンチの良い判断だといえよう。
・それでもトードーの怒りは収まらない。蹴飛ばされる机に、飛ばされるコケの入った瓶。
メンチはすかさずコケの瓶を取る。その行為から「どれほど貴重か」というセリフがよくわかる。皆は1時間で驚きと称賛を示したものの、メンチにとっては1時間もかけないと取れないものであり、とんでもなく貴重なのだということが伺える。
・トードーに応戦し、「どのハンターを目指すとか関係ないのよ」「誰だって武術の心得があって当然」と述べる。
ハンター試験が実は二段構えであり、裏試験は念習得が関門である、というのは、戦闘能力を上げる目的があったから、というのは後々に描写されるが、ここのメンチのセリフはその伏線とも言えるものだ。ハンターを目指すなら、誰だって戦闘能力は必要なのだと伝えてくれている。
そして、メンチはここで足のみで応戦している。獲物を使うこともない。メンチの戦闘面における実力の高さも表現しているシーンといえよう。
Bパート
・飛行船でネテロ会長が現れる。
「あのメンチが緊張しまくってやがる」
「それほどの人物ということだ。(差し詰め私たち受験生にとっては救いの神っていうところか)」
とレオリオとクラピカが言葉を交わす。
飛び降りても足の骨も折らず、クレーターができてしまう威力、「会長」という肩書き、そしてこの会話。ネテロが途方もなく強く、偉い人物なのだと瞬時にわかる。
・メンチは正直に告白し、ネテロに頭を下げ謝罪をする。
今までの絶対に譲らない、という姿勢を見せてきたメンチの姿から少し意外な行動とも言える。
料理への並々ならぬこだわりを持ち、プライドや誇りもあるが、素直さや誠実さも併せ持っていることがここでわかるのだ。
「正直な娘じゃ」「料理に対する情熱の証というわけじゃ」
とのネテロの言葉にも視聴者は頷く他はない。
・再試験はマフタツ山に生息するクモワシの卵を取ることとなる。
「こんなもんまともな神経で飛び降りれるかよ」と崖下を覗き言うトードー。
このセリフの通り、ここがハンターへの境のようなものなのかもしれない。崖を飛び降りて糸を掴む、そして卵を取って糸をつたって帰ってくる、このような一連の流れをスムーズに行うことができないのであれば、務まらない仕事だと言うことだ。
「あーよかった」
「こういうの待ってたんだよね」
「走るのやら民族料理よりよっぽどわかりやすいぜ」
「同感だ」
と、キルア、ゴン、レオリオ、クラピカ。
さすが「まともな神経」ではない4人だ。キルアは元暗殺者で、ゴンは山育ちであり、また人とは少し違った精神力があり、レオリオはトラウマを持ちつつも医者を志し、クラピカは復讐という暗い目的をうちに秘めた、変わり種ばかりだ。
まさにレオリオのいう通り、わかりやすいものの方が実力を発揮しやすく、ゴンのいう通り、「待っていた」のだろう。
・その4人に続いて他の受験生も飛び降りていく。
その際、トードーも降りるものの、ゴンを蹴落とし、卵を奪う。すると、そのタイミングで親鳥が襲ってくる。反動で落ちるトードーを、ゴンはすぐに糸から手を離し、釣竿を使って助ける。
先ほど蹴られたばかりだというのに、彼を助けられる、ゴンの人助け精神には躊躇いや迷いなどは一切ない。見ていて清々しいほどだ。
メンチの「変わった子ね」との発言も無理からぬことだろう。
そして、「ゴンは甘い」というような感想を持っている視聴者たちもいるかとは思うが、ここまでくれば、その口も閉じざるを得ないのではなかろうか。「ゴンはそういう子で、だからどことなく惹かれるのだ」と受け入れることもできるのではと私は考える。
・しかし、ちゃっかり卵を奪い返していたゴン
メンチの「なんで助ける気になったの?」に対し、「助けてって言われたから」と笑顔で答える。
命は助けるが、奪われたものはきちんと取り返すところに、甘さのかけらは見られない。この単純でわかりやすい、裏のない性格ゆえに、周りの人たちはどんどん惹かれていくのだろう。
・各々受験生たちは、メンチにもらった普通のゆで卵と食べ比べをする。クモワシの卵の味に感動する面々。その中でハンゾーは「命懸けでとってきた甲斐があったってもんだぜ」と述べる。
ハンゾーの言葉はまさにこの場面にぴったりのものだろう。料理はその過程を含めて料理である。自分でとってきて、作り、皆で食べ、味に感動し、分かち合う。それもまた、メンチの心に息づく料理への魂であり、魅力なのだろう。もう他の誰も料理「ごとき」やら、料理「なんか」などと言わなくなるだろう。
メンチもその後のシーンで美味しいものを発見した時の喜びや感動は手配犯を捕まえた時や金を手にした時に負けない、と言っている。
まとめ
人には誰しもその人の中に響く「何か」が必ず存在する。しかし、それは個々で違ってはいても、共感できないものはごく僅かであろう。
その人がその「何か」を語るときの目は純粋に輝いているはずで、譲れないもののはずだ。それを分かち合うことの大切さや、その「何か」に巡り会うために未知を探ろうとする好奇心が重要なのだと教えてもらえる、ギャグを挟みつつも深みのある回だったと言えるだろう。


